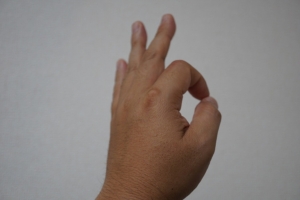第一図 尋牛(じんぎゅう)

荒野にポツンと一人たたずむ私。それまで生きてきた世界と同じに見えるが、実は全く違う世界。周囲には誰も居らず、自分と同じものを見ている人は居ない。全くの手探りでの再スタート。歓喜を抜きにすればこんなもの。これもまた偽らざる悟りの風景。
第二図 見跡(けんせき)

悟りの世界、あるがままの世界における唯一のリアリティと言える、ある種の法則を自力で発見するか、先人が残した教えを我がものとするべく学び始める時期。自らが悟るまでは、何が真の教えなのかも解らない。つまり、足跡を足跡と認識する事すら出来ない。
悟りたてホヤホヤの段階では、先人の完成した智慧と、今現在の自分の智慧の状態には、まだまだ距離がある。祖師方の仰られている事の中にも、解らない所が多くある。
先人の教えを勉強したり、我が身に起きた事を分析し、まとめる作業が絶対的に必要。これをサボると、いつまでたっても先人との距離が縮まらないし、先の「得牛」で大コケするのは必至。
第三図 見牛(けんぎゅう)

悟りや智慧が熟れてきて、新しい世界のおおよその姿を把握する事が出来る様になってくる時期。縁起や空性といった理法を用いて、法を語れるようになる・・・と言うか、偉そうに語りたがる。この段階だと、まだ悟りなるものが存在すると考えており、それに強く執着している。禅では「悟りを持っている」といわれる病的な状態。
第四図 得牛(とくぎゅう)

現実社会の在り方と、悟りとの乖離や対立に悩み始める時期。「真実はこうなのに、何でテメエら解ろうともしねぇんだよ!」とか「夢(妄想)ばっか見てんじゃねえ、(無我という)現実を見ろ!」とばかりに大暴れ。言っている事は正しいだけに救いがない。
法にも実体は無いと理解したり、仏法あれば世法ありと納得し、折り合いをつけるまで、何かと大変。悟っている事をひた隠しにして生活するか、人間社会に見切りをつけて隠遁生活をし始めたり、悟りの純粋性のみを認めて禅寺や道場で坐禅に耽る人もいるかも知れない。
基本的に仏法と世法は、水と油。如何にして悟りを生きるかは、終生のテーマである。
第五図 牧牛(ぼくぎゅう)

悟りを捨て始める時期。無いものは無い。悟りも無い。無い無い無い、何にも無い。でも、その手の中には、まだ「無」と言う残滓が残っている。
第六図 騎牛帰家(きぎゅうきか)

あらかた学び終わり悟りが安定してきて、その階梯における智慧がほぼ完成し、やっとの事で本当に楽になる時期。気が向くと「凡聖一如」的な法句を残したりするかも知れない。
第七図 忘牛存人(ぼうぎゅうぞんにん)
悟りを超えた悟りや、悟り無き悟り、迷いも悟りも無い静寂を知る時期。しかし、まだ悟りがあるとか、悟りを知っていると言う思いが残っているので、調子に乗ると聖人ぶったりしてしまう。
第八図 人牛倶忘(にんぎゅうぐぼう)

悟ろうが悟まいが、何も違いは無い。ぐるっと一周して振り出しに戻る時期。完全に元の木阿弥。振り返ってみると「何だったんだ今までのアレは」と目が覚める様な思いがする。でも以前と違って、もう二度と以前と同じ理由で迷ったりはしないし、自分はもう、自分じゃない。飽くまでもループではなく、スパイラル。
第九図 返本還源(へんぽんげんげん)

良いも良し、悪くても良し、これで良し、お前に良し、俺に良し、うん、良し。雨降らば降れ、槍降らば降れ。艱難辛苦なんのその。日々是好日、あっはっは矢でも鉄砲でも持ってこいッ。
でもやっぱ何事も無い方が良し。平和で楽な方が良し。・・・などと言う様な事を思う時期。端から見れば、脳天気な俗人と大して変わらないという境地。
第十図 入鄽垂手(にってんすいしゅ)
僧に非ず、俗に非ず。聖でもなく、凡でもない。我は我なり、我は我ならぬなり、我ならぬ我こそ真の我なり。だが、それが何だというんだ。所詮、何も分からんとあっけらかん。阿羅漢がここまで来たら、全ては終わり。他の階梯に居る者は、次の階梯に登るべく一から出直し。